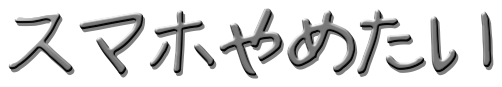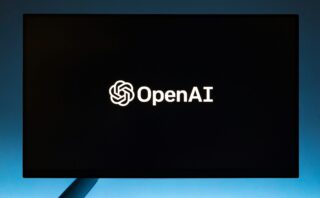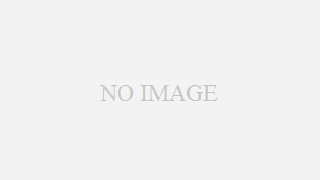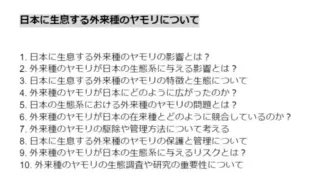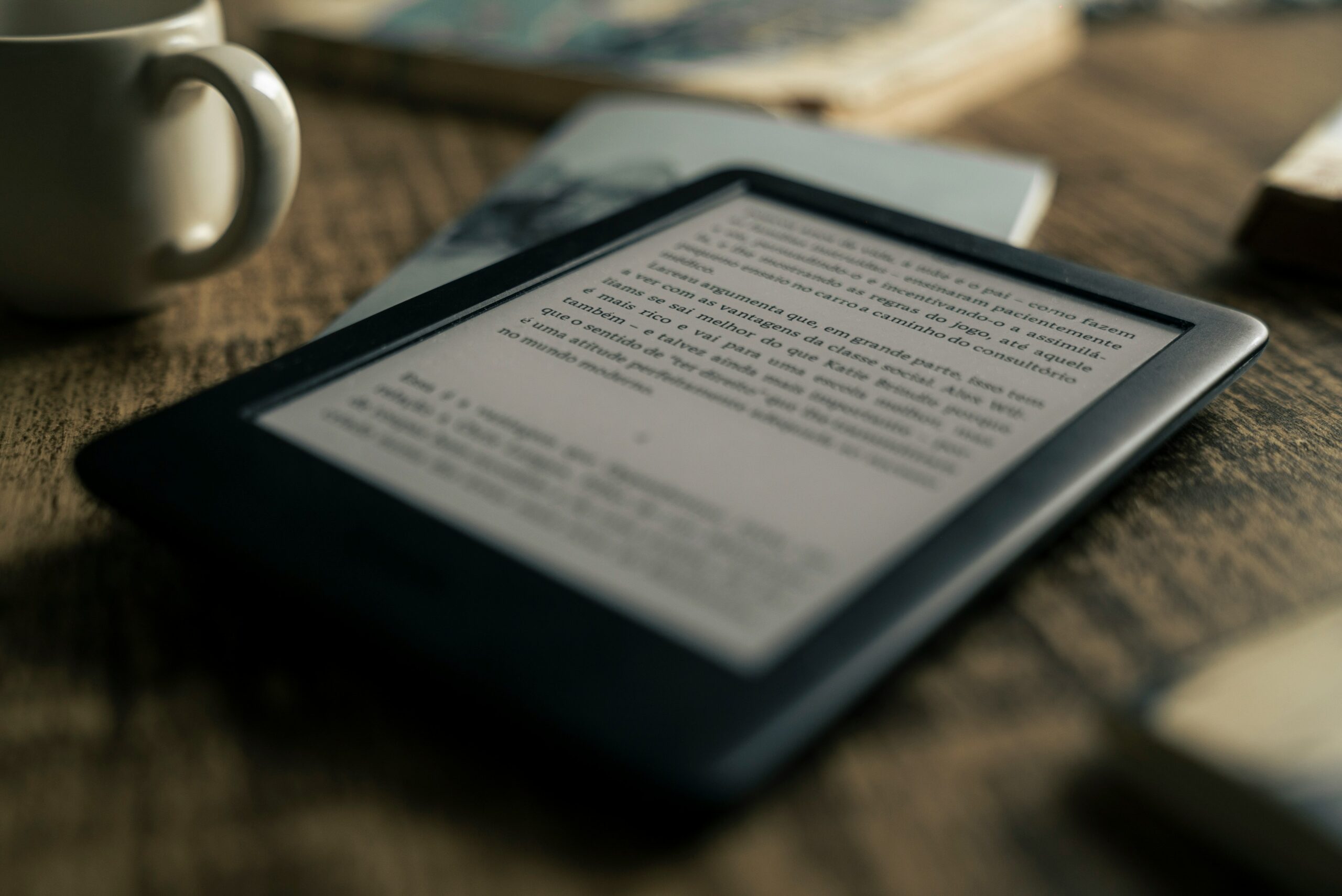吉本ばななさんの偽Kindle?:AI利用の電子書籍と著作権に関するニュースが気になる
AIを利用して作ったとみられるキンドル電子書籍が吉本ばななさんの著作物に似ており、吉本さん本人の名前もその著者であると誤認されるようなかたちで使われていた。
そのことを自身のファンの方から連絡を受けて知った吉本さんが、その著者に出版差し止めを求めたというニュースが話題になっている。
偶然昨日私はGoogleアドセンスに合格し、AIを利用した記事作成についてきちんと知識を持たないと怖いなと思っていた。これを機会に、AIを用いたリライト・二次創作と著作権(著作権侵害その他の法的リスク)について、今まで不安に思っていたことを調べてみた。
XServer VPS for Windows Server
1. 著作権と二次創作について
著作権とは何か?
創作された文章・画像・音楽・映像などの表現物に対して、創作者が持つ法律上の権利。
日本の著作権法では、著作物の使用に関して、無断での複製や改変を禁止する条項が設けられている。
後述するが、著作権侵害は親告罪である。
二次創作とは何か?
既存の小説や漫画、アニメなどを基にして、新しい作品を作る行為を指す。同人誌やファンアートなどが代表例。本来、著作権法においては、原作の著作権者の許可なく二次創作を行うことは「翻案権」の侵害に当たるため、違法とされる可能性がある。
しかし、日本では二次創作の文化が根付いており、取り締まりが厳しく行われていない。
大手企業の現役面接官が運営する就活エージェント【ユメキャリAgent】
2. 二次創作は違法?訴えられないのはなぜ?
結論から言うと、二次創作は原則、著作権侵害に該当する。しかし、著作権者が訴えないケースが多い。
二次創作が訴えられにくい理由
著作権者が容認(黙認)している場合が多い
まず、著作権者や出版社がファン活動としての二次創作を明確に認めているケースが一部ある。
一方で、著作権者・出版社が著作権について明言していない・認めていない場合でも、日本においては『クリエイターのファンを増やすことに寄与する』という風潮もあり、著作権者に無断で二次創作が行われることも多い。
訴訟に膨大なコストがかかる
著作権を侵害されたとしても、訴訟をするためには、時間や費用、精神的労力がかかる。著作権者にとって、小規模の個人すべての二次創作活動を逐一指摘し、法的措置を行うメリットが少ないため、黙認している場合がある。
著作権者に対する商業的影響が少ない場合が多い
コミケなどで販売される同人誌の多くは、限定的な場所での販売であったり、小規模の商売であったりする。公式作品の売上には影響を与えにくいと判断し、黙認している場合がある。
高品質SEO記事生成AIツール【Value AI Writer byGMO】
二次創作に対し、著作権者が法的措置を取るパターン
ただし、例えば以下のような場合、著作権者は法的措置を取る可能性がある。
- 著作権者が明確に二次創作を禁止している場合
- 公式と誤認されるような作品である場合
- 大規模に商業販売を行い、原作の市場に悪影響を及ぼす場合
つまり、二次創作が訴えられないのは「合法だから」ではなく、単に「著作権者が動かないから」。
例えば、著作権者の方針が変わったり、新たなルールが適用されたりすると、それまで黙認されていたものが突然、取り締まりの対象になる可能性がある。
著作権者である企業や個人が著作権侵害として指摘し、訴えれば、法的に争うことになる(特に営利目的での販売などはリスクが高い)。
3. AIに他者の著作物を入力して書かせた記事を、アフィリエイト目的のブログに投稿する行為の解釈
AIやデータサイエンスが学べる就労移行支援【Neuro Dive】
近年、AIを利用して記事作成を行う手法も増えている。私も実験的に、そのような行為をしている。
しかし、他者の著作物(小説・記事・PDFなど)をAIに入力しリライトさせる行為については、著作権侵害のリスクが高いように思っていたし、分からないと緊張していた。なのでこの際、調べてみた。
※私は普段、他者の著作物やネットの記事のコピペを基にしたリライト・要約ではなく、自身の考えを基に対話をした上で『ここまでの内容を記事にする構成を考えて』『その構成でSEO記事を書いて』と命令し、その出力を叩き台として記事を作っている。
この場合、翻案も意見も私本人のものだろうと考えている。調べ物を効率化してもそれが一般的な知識の範疇、かつアウトプットされたものに他者の意見との類似性がなければ、アウトプットに他者の著作権は発生しない?
偶然の一致などの場合、もしかしたら問題になるのか。違法・合法とは何ら無関係で、業界独自の指標にすぎないコピペ率を減らす工程も、その観点で見れば意味を持ってくるのか。今後も調べていきたい。
AIリライトと著作権の関係
AIを使った『リライト』(≠翻案作成・オリジナル記事作成)において、問題になりうることをまとめてみる。
全て、著作権者の許可があれば問題ない・AIを使ったとしても行動主体は人間であると思っておくと、安全かと思いました。
「複製権」の侵害
- 著作権法では、著作物のコピー(複製)を作成する権利は著作権者にある。
- AIに全文または部分を入力すること自体が、著作権者の許可なしに「複製」している行為とみなされる可能性がある。
- 要約・抜粋でも、著作権侵害を認められたケースがある(?もう少し調べる)
「翻案権」の侵害
- AIがリライトしたとしても、元の著作物の本質的な表現を維持したまま 再構成した場合、翻案(改変) に該当するとされる場合がある。
- 著作権者の許可なしに行うと違法となる。
「公衆送信権」の侵害
- ブログに投稿して広告収入を得る行為は「公衆送信」(不特定多数への公開)に該当し、著作権者の許可なしに公開すると違法となる。
「コピペ率〇〇%以下なら問題ない」?
ブログ記事の執筆時に「コピペ率〇〇%以下」という指示が出されることがあるが、これはSEO(検索エンジン最適化)対策の基準であり、著作権の観点では無関係。
- コピペ率が低くても、元記事の構成や論理展開が同じなら著作権侵害の可能性がある。
- AIがリライトしたとしても、著作権者の許可なく元記事を基にしたり、入力している時点で問題となる可能性がある。
Googleからペナルティを受けるリスクもある?
SEOの観点からも、AIによるリライト記事は問題視されている。
- Googleは「オリジナルコンテンツ」を重視しており、AIリライト記事は今後ペナルティの対象となる可能性もありそう。
- 著作権者がDMCA(デジタルミレニアム著作権法)申請を行えば、Google検索結果から削除されることはありえる。
リライトで訴えられるリスクは?
- AIを使ったリライト記事であっても、元記事の著作権者が問題視すればすぐ、法的措置の対象となりうる。
- AIが作ったものでも、目的と行為の主体はあくまで人間。AIが作ったものであれば、すべて法的に問題がないわけではない。
まとめ
今回、主に自分のために勉強としてまとめました。
そのうち、レントラックスさんやA8ネットさんのイベントなどで、AIやアフィリエイト関連に強い法律事務所さんなどとお話する機会がもしあれば、インタビューを申し込んでみようかと考えている。
自身がブログ収益化に挑戦しているが、同時に(特に文章系の)AIを含むデジタル全般について、主に個人事業主様に対するツール選定や効率化の提案、また一般の方に向けた個別レクチャーを行っている立場なので、このあたりはアンテナを高く張っていきたいと思っている。